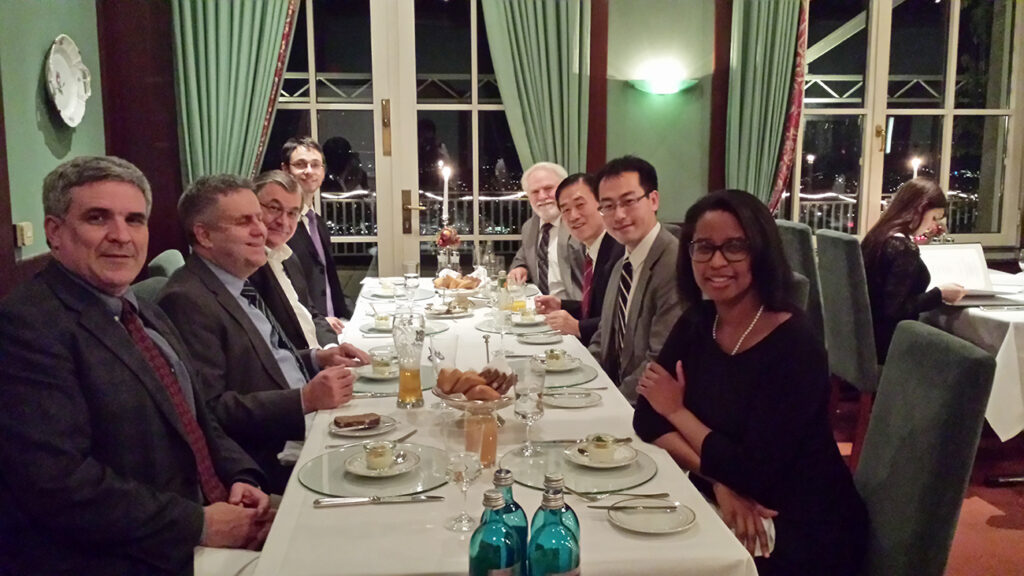
Ⅰ. 香油の入った壺を壊した女性と世俗的な正義の衝突
マタイの福音書26章には、イエス様がベタニアのツァラアト(重い皮膚病)の人シモンの家におられたとき、一人の女性が非常に高価な香油の入った壺を壊して、主の頭に注ぐ場面が描かれています。当時の文化的・社会的背景を考えると、この女性は財産の一部とみなされるほど弱い立場に置かれ、また社会から疎外されやすい存在でした。さらにルカの福音書7章では、涙でイエスの足を洗い、香油を注いだ女性が“罪の多い女”として描かれています。しかし、そのような世間的な評価に関係なく、彼女は主の無条件の愛を悟り、最も尊く貴重なものを喜んで捧げたのです。その行為は当時の弟子たちにさえ浪費と映り、とりわけイスカリオテのユダには激しい怒りや不満を引き起こしました。
弟子たちは「この高価な香油を売れば貧しい人々を助けることができたのではないか」と主張しました(マタイ26:8-9)。一見すると、その言葉は正義にかなった、論理的で現実的な意見にも思えます。しかし、実際に彼らが知るべきであった最も重要で深遠な世界、すなわちイエス様が示された「浪費にも見えるほど豊かな愛」を、弟子たちは見逃してしまいました。もちろん貧しい人を助けること自体は神の御心に適った尊い行いです。けれどもここで弟子たちは真に貧しい人を助けようという思いではなく、自分たちを正当化するための論拠としてそれを持ち出したに過ぎなかったのです。ヨハネの福音書12章6節によれば、ユダは金銭入れを預かっている立場を利用し、その中から盗みを働いていたとあります。彼の憤りは“貧しい人への愛”ではなく、別の利益や自己中心的な考えから出たものであったことが暗示されます。結局、ユダはイエス様が地上に来られて示してくださった無条件の愛、つまり愚かと思われるほどにあふれる愛の価値を理解できず、この事件をきっかけにますます心を閉ざしていきました。
張ダビデ牧師はこの場面を深く黙想し、「イエス様の愛を最も間近で見ていたはずの弟子たちさえも、その愛を理解できなかったとき、それがユダの裏切りへとつながった」と強調します。主のすぐそばにいるということは大きな祝福ですが、同時に常に目を覚ましていなければならないことでもあります。近くで聞けば聞くほど、近くで見れば見るほど、もっと深い恵みと愛を体験することができますが、もしその愛の“浪費性”を理解せずに世俗の基準で判断してしまうと、大きな誤解を招きやすいのです。主の最も近くで仕え、助ける役割を担っていたはずのユダが、結局は人間的な正義や欲望、そして歪んだ判断に支配され、主を売り渡すに至ったという事実は、私たちに悲劇的な教訓をもたらします。
「なぜこんな無駄遣いをするのか?」という弟子たちの問いかけは、人間的な知識や世俗的な尺度では到底理解しがたい、しかし限りなく大きく深い愛に対する一種の反発だったとも言えます。これは、やがて銀貨三十枚でイエスを引き渡すという極端な結末を予告する問いでもありました。一人の女性は高価な香油を惜しみなく注いで主への愛を表したのに、その女性をむしろ「無駄だ」と批判し、「憤慨」した弟子たち、特にユダは、自分自身がどれほど深く「師の恵みと愛のうちに養われてきたか」を忘れていたのです。このように私たちも主を信じ従っていると自負しながら、神の愛を世俗の尺度で測ろうとしてしまうことがあります。それが、いくらもっともらしく合理的で現実的に見えたとしても、主の国においてはむしろ愛の栄光に満ちた実体を見失ってしまう近道になり得るのです。
張ダビデ牧師は、こうした姿は私たちの信仰の中にもいくらでも再現される可能性があることを想起させながら、主の聖なる浪費と愚かに見えるほどの愛に対して、あざけりではなく畏敬の念を抱くべきだと強調します。ぶどう園の労働者のたとえ(マタイ20章)や放蕩息子のたとえ(ルカ15章)、さらにヨブ記の苦難物語に至るまで、聖書のあちこちで示される神の愛は、しばしば非常に非合理的に見えます。しかし、その愛は私たちの計算や理解を超え、私たちを救おうとする神の絶対的で無条件の切なる思いから発するものであり、それこそが私たちが拠り頼むべき真の真理であり命の道なのです。
結局、香油の壺を壊した女性が示した美しく献身的な愛を前にして、ユダや弟子たちの世俗的な正義感はゆがみます。「良いことをする」という大義名分のもと、「貧しい人々にもっと利益を与えるべきだ」という理由のもと、さらには「この人は人々を間違った方向へ導いている」というねじ曲げられた判断のもとで、主を排除しようとする流れが生まれます。その結果、ユダはごくわずかな額である銀貨三十枚でイエスを売り、自らの魂をも破壊する道へと踏み込んでしまうのです。
Ⅱ. ユダの裏切りと無条件の愛:張ダビデ牧師の黙想
銀貨三十枚という値で主が売られたことは、人類史上最も悲しい裏切りの象徴として残っています。創世記にはヨセフが兄たちに銀貨二十枚で売られた物語が出てきます(創37:28)。しかしヨセフの場合は神の摂理のうちに、その裏切りさえも善へと変えられる驚くべき結末が示されています。一方イエス様の場合は、人類の罪を贖うためにご自身が進んで十字架の道を選ばれたという点で、その裏切りの重さははるかに大きく、深い意味をもっています。ユダは主に銀貨三十枚を受け取って引き渡した瞬間、自分の内面でずっと燃え上がっていた誤解や不信、そして利己的な目的が最終的に決定づけられてしまいました。どんなに主のそば近くにいても、主の愛を世俗の論理でゆがめてしまった瞬間、すでに彼の魂は崩れていたのです。
主は日頃からユダを深く信頼しておられました。弟子の中でも金銭入れを託すほど彼を信じておられ、これは「人選を誤った」という意味ではありません。イエス様は最後まで、そして絶対的に弟子たちを愛されたのです(ヨハネ13:1)。しかしその愛を受けとめる各人の心構えはさまざまでした。ある人にとっては、その愛が存在全体を変える力になりましたが、ユダにとっては最後まで受け入れがたい負担や不満の種になってしまったのです。これについて張ダビデ牧師は「イエス様の愛は理由を問わない完全な愛であり、私たちがその愛を部分的にしか受けとめず理解しようとしないならば、必ずゆがみが生じるのだ」と語ります。
主が示された変わらぬ哀れみと恵みは、人間的な視点で見ると「あまりにも愚かで不公平」に感じられるかもしれません。ぶどう園の労働者のたとえのように、朝早くから働いた者と夕方遅くに少し働いただけの者が同じ賃金を受け取ると、私たちは素直に「不公平だ」と考えやすいものです。放蕩息子のたとえでも、結局すべての財産を浪費して帰ってきた息子に対して父親はむしろ宴会を開き、喜び迎えます。その様子は真面目に父のそばに仕えていた兄にとっては不合理に映ったことでしょう。こうした場面に共通するメッセージは、神様の愛が私たちの常識や理屈をはるかに超えているという点です。
ユダが陥った落とし穴は、キリストの愛を合理的な尺度で計ろうとしたことでした。彼はおそらく「もし主が本当に神の国を打ち立てる方なら、こんな浪費めいたこと(香油を壺ごと注ぐ行為)を許すべきではない。正しいかどうかを見極めて、貧しい者へより効果的に愛を施すべきではないか」というような思いをふくらませていったのかもしれません。ところが、キリストが示された愛は世の観点から見れば非効率的であり、ときには愚かしく、浪費にさえ見えることがあります。イエスは罪人を受け入れ、無価値とみなされる人々のためにご自身をまるごと注がれました。そのような愛は世の目に映せば「無駄遣い」であり得るでしょう。しかし神の目からすればそれは聖なる“浪費”であり、救いのための絶対的な愛なのです。
決定的だったのは、ユダがこの「香油の壺の事件」の後、大祭司たちのもとへ足を運んだことです(マタイ26:14-16)。「彼をあなたがたに引き渡せば、いくらくれるのか」と問う彼の言葉は、あまりにも悲しく、苦い響きをもっています。イエス様を奴隷のように売り渡す決断をしたわけです。その対価は銀貨三十枚――主を「激安価格」で売ってしまったことになります。主に深く愛された弟子が、長い間恵みのうちをともに歩んできた弟子が、わずかな金で主を売ろうと心に決めたとき、その内面には「この方は人々を誤った道へ導いている。私たちが追い求めるべき世の正義とは相いれない」というゆがめられた信念が存在していたのかもしれません。愛を正しく理解しないならば、その愛の持つ力を拒否して「これこそ間違いだ、取り除くべきだ」と結論づけてしまうことがあり得るのです。ユダの裏切りは、まさにそうした愛への拒否が極限に達した結果でもありました。
しかし主を売ってから、ユダはようやく自分の内に沸き上がる良心の声を聞くことになります(マタイ27:3-4)。自分が売り渡したお方が罪のない方だったと気づき、その銀貨三十枚を再び大祭司たちのもとに持って行き「私は罪のない血を売り、罪を犯した」と告白しました。裏切りの前には、自分の期待を満たすものだと思われたそのお金が、すべてを成し遂げた後にはむしろ彼自身をみじめにするだけの存在となってしまったのです。彼の後悔はあまりにも遅く、最終的には自ら首をつって死へと追い込まれました。その経緯を見ると、主の愛があまりにも遅れて思い出されたのだと感じます。愛を信じることも、改めて立ち返る勇気も得られなかった彼は、絶望の淵に飲み込まれてしまいました。
ここで張ダビデ牧師は「ユダは本当に、もう一度主のもとに戻ることができなかったのだろうか」と問いかけます。放蕩息子の物語では、すべてを失い果てた息子でも父のもとへ帰りさえすれば、大宴会で迎えてくれる神様の御心が垣間見えます。主はすでに敵さえも愛し、十字架の上でご自分を嘲る者たちをも赦されました。その無条件の愛の前で最後まで心の扉を閉ざしたのはユダ自身です。彼は「自分は主を裏切ったのだから、もはや戻ることなどできない」と思い詰めたのかもしれません。しかし、もし彼が悔い改めて主のもとに行くならば、主は確かに彼を受け入れてくださったはずです。私たちはこの事実を忘れてはなりません。主の愛は人間的な基準で途切れたり消え去ったりすることはないのです。
ユダの姿は、逆説的に今日の私たち自身を振り返るきっかけになります。教会の中で、あるいは信仰の中でイエス様の教えを聞き、礼拝をし、神様の愛を口にしながらも、実際の生活においていつの間にかその愛を世俗的な基準で測り、歪んだ熱意で批判してはいないかを点検する必要があります。そして、もしある瞬間に「主を離れる道」を選んでしまったとしても、再び戻る道はいつでも開かれていることを忘れてはなりません。放蕩息子が家に帰ってきたとき、父親が駆け寄って彼を抱きしめたように、その愛の懐は常に私たちを待っているのです。
Ⅲ. 聖なる浪費と十字架:ユダが見失った道、そして私たちの道
イエス様に出会った多くの人々、特に取税人や娼婦、社会的に疎外された人たちは、その愛がどれほど無条件に注がれるものであるかを生々しく体験しました。彼らは律法的な基準では罪人にすぎず、社会の常識によって“無価値な存在”とみなされることさえありました。しかし、主は彼らと目を合わせ、憐れみと慈しみを示されました。主が築かれる神の国は、私たちの理解や知識をはるかに超えて、ときには浪費にも見え、不公平にも映るほどの愛によって成り立っているのです。そしてその愛の頂点を示す出来事こそ、十字架の死と復活です。
張ダビデ牧師は「十字架こそが最大の聖なる浪費であり、同時に最も深い愛の証なのだ」と語ります。神であるイエス様が、罪のない方として罪人の代わりに死なれたのですから、世的な観点からすればこれ以上ない“理不尽な浪費”はあるでしょうか。私たちは一体何者であって、神の御子がご自身の体を差し出し、血を流されるほどの価値があるというのでしょう。しかしこの浪費がなければ、私たちはいまだ永遠の罪の刑罰から逃れ出る道がありませんでした。愚かに見える十字架の犠牲こそ、人間に対する神の救いの計画であり、絶対的な愛の表れなのです。
イスカリオテのユダは最後まで、この「聖なる浪費」の意味を理解しませんでした。香油の壺を壊した女性を見て「無駄遣いだ」と非難したあの心が、イエス様がご自分を完全に差し出してくださる十字架の出来事へとつながるとは、彼には想像もつかなかったのでしょう。結局彼は自らの手でその道を用意することになってしまいました。浪費としか思えないほどの愛の極みに対して、「愚かな行為」とみなし排除しようとし、大祭司たちにイエスを引き渡す道を選んだのです。けれども主はその選択さえも、人類に救いをもたらすための十字架への道として用いられました。十字架の上で流された血によって、全人類に永遠のいのちへの道が開かれたのです。
私たち一人ひとりは、この愛の前でどのような態度をとるでしょうか。もし世の観点で主の愛を測ってしまうなら、十字架の真意を完全に悟ることはできません。信仰が消え失せるとき、人間的な知識や論理がかえって私たちの目を曇らせてしまうのです。聖書で「善悪を知る木の実」を食べてはならない(創2:17)と命じられたのは、「人間が自分の知恵で善悪を決めようとするな。神の言葉に従い、神が与える愛のうちにとどまりなさい」という警告でもありました。しかし私たちはときどき、自分の頭を働かせ、「この愛は本当に正しいのか? この状況は非効率なのでは?」と考えて、主の全き導きを疑ってしまうのです。その結果として罪を犯し、霊的に破壊されてしまうと同時に、主なしに生きる人生の虚しさと苦しさを後になって痛感することになります。
張ダビデ牧師は「主を裏切るということは、ただイエス様を否定するという意味合いだけではなく、その方の愛を世俗的論理で拒絶し、教会共同体や信仰の中で行われる無条件の愛と献身をあざける心が宿ったとき、すでに始まっている」と言います。愛は関係の深まりを通して完成していきますが、その深い関係には必然的に“浪費とも思える時間”と犠牲が必要です。親と子の関係を思い出すと分かりやすいでしょう。子どもを育てるには終わりのないほどの犠牲とエネルギーが費やされます。しかし親はそれを浪費だと思わず、喜びとして担っていきます。子どもが生まれ、育っていくすべての瞬間が愛の実践であり、その愛のうちで親自身も喜びを味わうのです。
主が弟子たちを、そして私たちを世話してくださるときも同じです。その愛は無条件であり、時に未熟な私たちをそのまま抱きしめる大きな愛です。これこそが神の憐れみであり、聖なる浪費なのです。ユダはこの愛の本質を誤解し、自分の基準で判断して「こんなことを続けさせるべきではない」と結論づけました。そして銀貨三十枚という対価で師を売り渡しました。結果として彼は、求めていたはずの世俗的正義や利益さえ得られず、深い絶望のうちに自死を選んでしまったのです。
しかし私たちの物語はそこで終わりません。むしろこの悲劇の中にあってこそ、神の救いの奥義が明らかにされます。主はユダの裏切りさえも用いて十字架への道を完成され、その十字架の上でご自分を差し出されることによって、選ばれた子どもたちに永遠のいのちを与えてくださいました。これは私たちの罪がどのようなものであれ、私たちに対する神の愛は決して途切れることがないという決定的な証拠です。たとえ私たちがつまずき、裏切りの道を歩んだとしても、悔い改めて戻るなら、主は変わらず私たちを受け入れてくださるのです。
だからこそ受難節(四旬節)は、この無条件の愛と苦難を黙想する時なのです。私たちは主の前で自分の世俗的な知識や高慢を打ち壊す必要があります。ときには香油の壺を壊した女性のように、主に自分の全存在を注ぎ出す献身が求められます。それを「無駄遣い」とあざける冷笑的な声に直面しても、「これは主に対する聖なる浪費なのだ」と告白できる信仰が必要です。十字架の道は浪費に見えますが、その道こそが命への道です。主の愛に対する全き信頼をもってこの道を歩むなら、決して後悔することはないのです。
張ダビデ牧師は最後にこう勧めます。「私たちが持つすべてを主にお捧げしたとき、世はそれを浪費だとあざ笑うかもしれない。けれども主はそれを最も美しい献身として受け取ってくださる。マリアが主の足元に座って御言葉に聞き入ったこと、罪深い女が香油の壺を壊して香油を注いだこと、放蕩息子が戻ってきて父の懐に抱かれたことこそが、福音が証しする神の国の現実なのである」と。私たちはイスカリオテのユダの悲劇から学びつつも、決して同じ結末に陥らないように、主の愛を深く信頼しなければなりません。その愛は、一度たりとも私たちをあきらめない永遠の愛であり、最終的には私たちを変えて神の国のすばらしい証人としてくださる力なのです。
結局、選択は私たちに委ねられています。ユダのように「この愛は非合理だ」と言って裏切りの道を進むのか、あるいは香油の壺を壊した女性のように「この愛は自分のすべてを捧げるに値するほど尊い」と言って献身の道を歩むのか。そして、たとえ一度ユダの道を選んだとしても、いつでも主のもとへ戻ることができます。主は悔い改める一人の魂をも決して見捨てられません。では私たちはこれからどんな道を歩むのでしょうか。銀貨三十枚というわずかな金に縛られて神の国の栄光を失うのか、それとも主が示してくださった愛の深みを悟って、その道をともに歩むのか。その問いに対する答えこそ、私たちの信仰告白であり、日々の生活の中で現れるべき実践的な決断なのです。
www.davidjang.org